���̃G�b�Z�C�́A�����܂������Љ�l�ɂȂ���������̍��A�w������́A���Ƙ_���݂����Ȋ����ŏ��������̂ł��B�@�@�@![]() HP�g�b�v�ɖ߂�
HP�g�b�v�ɖ߂�
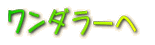 �@�@�@
�@�@�@�@�ڂ��炪��������ɂ�����A�����������Ăǂ�ȍs�����Ƃ邾�낤�B�܂��ړI�n�A�����ē����A�o���́A�����ċA��͉����E�E�E�E���Ɍv������A���l�͎ԑ���茩����l�Ɏ���ӂ�Ȃ���o�čs���B�@�y�G�b�g��芷���͉����ŁA�������ɂ��āA�����҂����Ԃ����邩��H�����āA���`���I�݂₰��������Ȃ�������E�E�E�E�z
Question �F
�ڂ��炪����Ă��闷�Ƃ������̂́A�A�邱�Ƃ�O��ɂ��Ă���̂ł��ˁB
�o������Ƃ��ɂ͂����A�҂�����Ă��āA���̕ӂ��s���Ƃ��Ȃ��B(�ܖ؊��V�j
�@���𑱂���ߒ��Ŏ�����i�炦�����Ƃ����w�͂��͂炤���A�����藷�ɑ��鏀�������Ă��̌v�搫�̂����ɓ��퐫�̉����ł����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̗l������������B������i�炦�����Ȃ��炻�̎��R�Ȉړ��Ƃ��Ă̗����A�o���������̎��_����v��Ƃ������Ƃ̎��ꑤ�ʂł�����K���ɂ����Ă��̐��_�ɂ����Ă����ۂɂ����Ă����퐫�ւ̃A�C�f���e�B�e�B�������Â������ƂȂ��Ă��܂��B
 �����w���̍ד��x���I���W�i���Ƃ�����{�̗��́A���̃p�^�[���Ƃ��čs���ċA���Ă��邱�Ƃ����̌`�ԂƂ��Ă���B�m�Ԃ́u�����͕S��̉ߋq�ɂ��āA�s�������N���܂����l�Ȃ�v�Ƃ������A�l���𗷂ƍl�����ꍇ���{�l�́A����y�Ɋ҂�Ƃ������z���Ƃ�B�܂�l���ɂ��Ă��s���ċA���Ă���ƍl����悤���B��������ɏo��ΉƂ��u������Ƃ����͖̂������ʂ̂悤���B�Ƃɂ́A�Ƒ������ĉ������H��������B�������u�̋��̎R�Ɍ������Č������ƂȂ��v�̊��o�ɑ�\�����悤�ɐ��_�I�̋��u�����Ƃ����͓̂��{�I�Ȃ��̂Ƃ��ċ��������̂ł͂Ȃ��̂��낤���B���Ƃ��A�A�����J�̐����ւ̃p�C�I�j�A�E�X�s���b�g�A�V�F�[��
come back �̂����炢�J�[�{�[�C�A�����ƑΏƓI�ȁA���q�˂ĎO�痢�A�Ђ���̂悤�ɕ��Q�˃g���u���ˎĖ��˕��Q�@�Ƃ������悤�ɂ��Ȃ�̋������Ď���̉ƂƂ̐��_�I�J�͋��͂Ȃ悤���B
�����w���̍ד��x���I���W�i���Ƃ�����{�̗��́A���̃p�^�[���Ƃ��čs���ċA���Ă��邱�Ƃ����̌`�ԂƂ��Ă���B�m�Ԃ́u�����͕S��̉ߋq�ɂ��āA�s�������N���܂����l�Ȃ�v�Ƃ������A�l���𗷂ƍl�����ꍇ���{�l�́A����y�Ɋ҂�Ƃ������z���Ƃ�B�܂�l���ɂ��Ă��s���ċA���Ă���ƍl����悤���B��������ɏo��ΉƂ��u������Ƃ����͖̂������ʂ̂悤���B�Ƃɂ́A�Ƒ������ĉ������H��������B�������u�̋��̎R�Ɍ������Č������ƂȂ��v�̊��o�ɑ�\�����悤�ɐ��_�I�̋��u�����Ƃ����͓̂��{�I�Ȃ��̂Ƃ��ċ��������̂ł͂Ȃ��̂��낤���B���Ƃ��A�A�����J�̐����ւ̃p�C�I�j�A�E�X�s���b�g�A�V�F�[��
come back �̂����炢�J�[�{�[�C�A�����ƑΏƓI�ȁA���q�˂ĎO�痢�A�Ђ���̂悤�ɕ��Q�˃g���u���ˎĖ��˕��Q�@�Ƃ������悤�ɂ��Ȃ�̋������Ď���̉ƂƂ̐��_�I�J�͋��͂Ȃ悤���B
�@���ɂ����鐸�_�I�ȃA�C�f���e�B�e�B�̂Ђ��Â���l����ɂ������ĉߋ����猻�݂܂ł̗��̎��̕ω����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o�C�L���O�A�}���R�|�[���A�R�����u�X�Ȃǃp�C�I�j�A����A�C���O�����h�̏��N�̋���M�����g���������т����j�̃��}���A�����Ȋo��ƗE�C�ł����ē��ݏo����������ߐ��̓��{�̗��@�����Č���̃��W���[�Y�Ƃɂ�������������ƁA���̔ɉh����h���b�v�A�E�g�����҂�̂����炢�̗��ȂǁB�������Ă���ΏƂƂ��Ă��闷�Ƃ͓��Ƀ��W���[�Ƃ��Ă̗��ł��邱�Ƃ��m�F���Ęb��i�߂悤�B
�@���݁@��肩����A���������l���������Ƃ������������ł��̐l���̐F�ǂ�⑧�ʂ��ɂȂ낤�Ƃ��Ă��闷�́A���ꎩ�̂��ǂ��v���o�̑n��Ɏn�I������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�A���Ă���ӂ�Ԃ茩��F�ǂ�����P���������̂ɂ��邽�߂ɘb�̂˂������A�ʐ^���Ƃ�o������߂悤�Ƃ���B����Ȃ��킵�Ȃ������肪�A���l�����ĕ�����点�Ă���悤�ł���B�O����A�O������̐��䂩��E���Ď��g�̗��Ă��K�͂ɏ]���čs�������A�����̂��̂��A�����^�����Ă������̂����炢�A���邢�͖`���Ƃ������l���������������̐��_�͂ǂ��ւ������̂��낤���B�͂Ă��Ȃ����̃��}�������ꂽ���̎���A�����l�����̂܂܂��ƌ�����m�Ԃ̐��_�́A���ǂ��ɁE�E�E�@�m���ɗ��l�l���͑��債�A�t�ɗ��͒Z���Ȃ����B���̕ω����A�������̂��A�܂��͎��オ����������̂��B
���ɗ��̎��ۂɂ����čl���悤�B���W���[�Y�Ƃ̔ɉh�ƂƂ��ɗ��͓���ł̎��O�̎葱���ɂ����Ă��̂����������Â�����悤�ɂȂ����B�h�̗\��n�܂��Ԍ���w��Ȍ�����V���A�͂Ă͗��s�̃p�b�N�ȂǁA�ڂ����ł����������v���͕̂x�R�\�M�Z�咬�����ԍ����A���y�����[�g�ł���B����͌��ヌ�W���[�Y�Ƃ̍ō���̂ЂƂƂ��v������̂ŁA������������{��̗������ւ���̂��B�܂������ɍs���Ɠd�ԁA�P�[�u���A���[�v�E�F�[�A�D�A�o�X�A�g�����[�Ɠ��{���ɂ����蕨�ɏ�邱�ƂɂȂ�B�����K�v�͑S���Ȃ����R�E�㗧�R�̎R�ł��z������킯�ł���B���̊ԁA�V���Ԃ��܂�A�����Ă������ƂȂ�ƂR�`�S���͂�����B�������s�����l�̘b�ɂ��A �f��قŃX�N���[�������Ă���̂Ɠ����A���̔����݂����ɂ݂₰���̂��₽��Ɣ����ɑ�������ʐ^���Ƃ��Ă݂��肷�邻�����B�ڂ��͂�����s�����Ƃ������Ƃɂ��Ă���ӂ�ł����Ȃ����o���ŕ⋭���悤�Ƃ����Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�����ė��s�̃p�b�N�Ƃ͂ڂ��ɂƂ��Ă͂��̉�������ɂ����l�����Ȃ��B�u���퐫��蓦�����Ă̗��v�Ƃ����l���������邪�A����ł͓��퐫�����������悤�Ƃ���s�ׂł���A�A�҂̂��߂̏o���Ƃ����������ł����Ȃ��B
�f��قŃX�N���[�������Ă���̂Ɠ����A���̔����݂����ɂ݂₰���̂��₽��Ɣ����ɑ�������ʐ^���Ƃ��Ă݂��肷�邻�����B�ڂ��͂�����s�����Ƃ������Ƃɂ��Ă���ӂ�ł����Ȃ����o���ŕ⋭���悤�Ƃ����Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�����ė��s�̃p�b�N�Ƃ͂ڂ��ɂƂ��Ă͂��̉�������ɂ����l�����Ȃ��B�u���퐫��蓦�����Ă̗��v�Ƃ����l���������邪�A����ł͓��퐫�����������悤�Ƃ���s�ׂł���A�A�҂̂��߂̏o���Ƃ����������ł����Ȃ��B
�@�����čł��ᔻ����邱�Ƃ́A����N���ɔ����Ă��܂������Ƃł��낤�B���R��n���X�P�W���[���Ƃ���ɔ�����ʥ�h����i����ɓ����B�����ău�[���ɒǏ]���Ă��܂������B�ڂ���ɂƂ��ĂƂ��Ă��M�d�Ɏv������̂�͂���Ă��܂������s�ҁA���̊�͐E��Ɍ������l�Ԃ̉���݂����ɔ����Ă���B�f�B�X�J�o�[�W���p���̃|�X�^�[�@��ʌ��Ђ̃p���t���b�g�@����炪�������o�����ł͂Ȃ��A�������o����̂͗��l�ł����Ȃ��B
�@���̗��l�Ȃ�̗���n�삷�邱�ƁA���̓����A���Ƃ��Ẵv���~�e�B�u�ȓ��������Ƃ߂悤�Ƃ��邱�ƁB�����i�炦�Ȃ���̎��R�Ȉړ��Ƃ��Ă̗��̒��Ɏ����Ȃ�̐�����ςݏd�˂Ă����B���퐫����͂Ȃꗷ���ꎩ�̂Ɏ���������������܂Ŏ���B�����^���Ƃ��Ă̗��A���ꂪ�ڎw�����̂��B
 �@�ܖ̕��͂̒��Ƀq�X�e���A�E�V�x���A�[�J�Ƃ����̂��o�Ă���B�V�x���A�̔_�v�����\�N�ƕ�炵�Ă��ā@�����Ɖł�����q�������āA�P�������Ă͉ƂA���Ă���_�v���A������ˑR�@������Ă��邤���ɃN�������o���ā@���������ƕ����Ă����Ă��܂��B�ǂ��܂ł��ǂ��܂ł������̕�����ڎw���ĕ����Ă����B���ꂪ�V�x���A���q�X�g���[�Ƃ����̂��������B
�@�ܖ̕��͂̒��Ƀq�X�e���A�E�V�x���A�[�J�Ƃ����̂��o�Ă���B�V�x���A�̔_�v�����\�N�ƕ�炵�Ă��ā@�����Ɖł�����q�������āA�P�������Ă͉ƂA���Ă���_�v���A������ˑR�@������Ă��邤���ɃN�������o���ā@���������ƕ����Ă����Ă��܂��B�ǂ��܂ł��ǂ��܂ł������̕�����ڎw���ĕ����Ă����B���ꂪ�V�x���A���q�X�g���[�Ƃ����̂��������B
�@����R�s�̋A�蒆�������𓌂Ɍ����������Ă����B����͍b�{�̂�����Ǝ�O�@�����삪�b�{�~�n�ɒ�����O�̖~�n�ł������B���́A��A���v�X�̎R�łɂ�����悤�Ƃ��Ă����B�܂��ɍL����c��ڂɂP�l�̂������N�������ɕЎ�����ɂ����ăJ�j���ŗ����Ă����B��������͗[�����Ȃ��߂Ă���悤���B�u�����������R�ɒ��ށ@���@�`�������悭�������B�������܂��撣�낤�v���̂悤�ȃC���[�W�������ԁA�����͖ؑ]�J�Ƃ��������邢�~�n���B�������ɂ͂Ȃ��炩�ɂ�������Ђ��������x�ւ̎R������B�O�҂Ƃ͂����������S�N����Z���Ă������{�̎R���̃C���[�W�A��������N�����̂ĕ����o�������̔_�v�̎p�͌���Ă��Ȃ������B�����ΏƂ������Q�ҁA���̒��ŁA�ڂ��͑O�҂Ɍ���Ȃ����i��������̂ł���B���֎q�𗧂��C���͂��Ė���J����B�Q�O����ɂ͍����Q�U�������A�[��̍������������钷������^�g���b�N�A�@�H�[�ɗ����e�w�����o�������Ԃ��𐅕��ɐL���B�K�[�K�[�@�v�X�v�X�@�V���A�K�[�L�`�[�ASTOP�u�H�[���u�H�[���E�E�E�u�ǂ�������܂���v�u�s���悫�H�E�E�E�E�E�E���E�E�E�ǂ��ł�������ł��v�@�u���̃g���b�N�́H�v�@�u�������炻���܂ŁB�v�t�H�[���t�H�[���@�K���@�S�H�[�@�u�H�[�E�E�E�E�E
�@�ڂ��̌������Ƃ͔����I�Ȃ��̂ł���B���������ăp�[�\�i���Ȃ��Ƃ͖ܘ_�ł���B���Ƃ͂��̖{ ���ɂ����Ĕ�Љ�I�Ȃ��̂ƍl����B���l�͂��ꎩ�́@�ނ�������Љ�ɂ����ẮA�ٖM�l�ł���A����R�@���R�ƕs���ƌǓƂƂ����L����B���̂R�҂ɂ��Č����A���R�̗��ʂ������A�s���ƌǓƂȂ̂ł���A���҂̑������������̏d���Ƃł��������̂ł��낤���B
���ɂ����Ĕ�Љ�I�Ȃ��̂ƍl����B���l�͂��ꎩ�́@�ނ�������Љ�ɂ����ẮA�ٖM�l�ł���A����R�@���R�ƕs���ƌǓƂƂ����L����B���̂R�҂ɂ��Č����A���R�̗��ʂ������A�s���ƌǓƂȂ̂ł���A���҂̑������������̏d���Ƃł��������̂ł��낤���B
�@�����q�C�ƕY���ɕ�����Ȃ�A�ڂ��̗��A�ڂ��Ȃ�ɖڂ������Ƃ��Ă��闷�Ƃ͕Y���ł��낤���B�q�C�Ƃ́A�ЂƂ̖ړI�n�����������̂ŁA�Y���Ƃ́A���ꂪ��j���Y�����Ă������Ƃ������B�Y���҂͂��̒��ŁA�H����{���������H�v������������Ƃ���B
�@�ڂ��́A���퐫���̓����̗��ł͂Ȃ��A�l���̒��̐F�ǂ�_�i�Ƃ��Ă̗��ȏ�ɗ����ꎩ�̂��ЂƂ̗������ɂ܂ŏ������邱�Ƃ����҂��@�����ā@���������ɂƂ��ĉ��炩�̑n�o�ւ̓y��ƂȂ��ׂ����҂���������̂ł���B���ۓI�ȕ\���͂��Ă����Ď��ۂɂ����ẮA�Ȃ�ׂ��������́@�����ĂȂ�ׂ������Ԃ́@�܂��Ȃ�ׂ����肬��ȓ��̓I���A����ȗ���������L�̂悤�����������Ȃ�Ƃ��ڂ��͊m�M���Ă���B�܂�L�̖ʂ��玿�I����_�I�Ȗʂ�I�o�����悤�Ƃ���̂��B

�@�����ɂ킽��A�������ŁA���肬��ȗ��A���̖k�C���̗��������������B�����ɓ��H����{�L�тĂ����B���̓����A�q��̋N���̒����ǂ��܂ł��܂������ɑ����Ă��邩������o�����B���ւ̏Փ��ȊO�̉����ł��Ȃ������B�������@���܂������Ƃɂ��̓��͖k�C���̐^������k�Ɍ������ĐL�тĂ�����ł����āA�ڂ��̉ƂւƂ͋t�����ɐi��ł��܂����B�Ȃ��Ȃ��̃T�C�t���������ڂ��̕s�K�ȗ��́A���̎�����n�܂����B�ڂ��́A�Ŗk�[�Ɍ������Đi�B�u�ǂ��ɂ��Ȃ���B�v�_���I������I���]�����ڂ��Ȃ���Ԃ������낤���A�ڂ��̉���ɂЂ���ł����I�v�`�~�X�g�́A�ڂ����ꕶ���ŏ@�J���ւ��ǂ蒅�������B
�@�A�邱�Ƃ��l�����A���ꂩ��P�����ڂ��͖k�C�����܂���Ă����B�o���ςȂ��̗��@���ʓI�ɋA�����Ƃ��Ă��s�������Ƃ����A��ł��������̗��B�Ȍケ�ꂪ�ڂ��̗��̌��_�ƂȂ����B
�@���Q�Ƃ������t������B�ڂ��́A�����m���Ă���B�����ɕ��Q���邪���Ƃ������炢�̗��ɏo���������Ƃ�����B�q�b�`�n�C�N�A�x���`�ɐQ����ԁA�����ƂɁA�_�Ђ̂����̉��ɐQ����ԁA��������������B�������@���܂悤���Ƃ��l���ł͂Ȃ������B�ڂ��́u���Q�v��m��Ȃ��u���Q�ҁv�����̂������ł���B�u���Q�v�Ƃ́A���̖{���I�ȈӖ��ɂ��������Ė����i�p�����ςȂ��@�����炢���̂��̂��l���Ȃ̂ł���B�R�ɂ��ꂪ��ʂɋ��e����Ă���l���A�܂�ΘJ�@�y�с@����ɑΒu���ꂽ���̂Ƃ��Ă̗]�ɁE���W���[�E�V�т𒆎��Ƃ����l���Ƃ͑�����Ȃ����Ƃ͖����ł���B���̂悤�ȑ��݂ɂ�����w���Q�x�Ƃ́A���݂̂ڂ���ɂƂ��Ăǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��l���Ă݂悤�B
�@�X�|�b�g���A�����J�Ɍ����悤�B�J�E���^�[�E�J���`���[�i�Η������j�ɂ���čs��ꂽ�A�����čs���Ă���w���Q�x�ɁA�@�J�E���^�[��J���`���[�Ƃ́A�P�X�U�O�N���茻�ۉ����A�f�U�W�N�ɂ��ꂪ�A���Ƃ@�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă������̂ł���B�q�b�s�[�ɑ�\����邱��́A�}�X�R�~�ɂ�蒷���E�~�B�X�e�B�V�Y���E�R�~���[���E�A�i�[�L�Y���@���̃T�C�P�f���b�N�Ȃ��������E�h���b�O�E�A���_�[�O���E���h�Ȋ��s�����ɂ��Љ�Ɉ�ۂÂ���ꂽ�B�U�O�N�㒆�������s�[�N�Ƃ��������̉^���́A���̂Ȃ��Ƀ��[�_�[�����āA�Ƃ��A�g�D���ꂽ�Ƃ����������̂ł͂Ȃ��A����Εs��`�̉^���ł������B�ڂ��́A���̃J�E���^�[�E�J���`���[�ɂ���ĒS��ꂽ�w���Q�x�@����ɂ�����w���Q�x���l���Ă݂悤�B
�@�����ŁA���Ȃ�L���Ȏ�i�Ƃ��Ă�������̂́A�A�����J���E�t�H�[�N�E�������t�H�[�N�E���b�N���������Ă������Ƃł���B���ۂk�o�R���̂����P�Ȃ́w���Q�x�Ɋւ���Ȃ��g���܂�Ă���B�̂́A���b�Z�[�W�ł��邪�A����ǖʂɂ����ẮA�r����������
�r�������������������̃��b�Z�[�W���͂Ȃ�āA���鐢��A�����̐S����A�l�����A�t�Ǝ˂��郁�b�Z���W���[�Ƃ��đ��݂���B�Ƃ肠�����A�S�O�`�T�O�N������ĐM����ɑ����ÓT���������Ă݂��B
�@�܂��A�A�����J�̈ꕔ�ł́A�܂��ɏ@���ȂƂ��������Ă����w�����u�����E�}���x�@�쎌���ȃn���N�E�E�B���A���Y�ɓo�ꂵ�Ă��炨���B �@�w���u�E�V�b�N�E�u���[�X�x�ŗL���ȃn���N�͉̂��@�u�ЂƂ̐l���ɏ�������ā@�����������܂�����Ă������Ƃ����ďo���Ȃ��͂Ȃ��̂����A��Ԃ̉����ƌy�����������Ŕ�яo�������Ȃ��Ă��܂��B��яo���Ȃ�������C�������Ă��܂����Ƃ��낤�B���͌N�������Ă��邯��ǁA�Ƃɂ����킩���Ăق�����A���͐��܂�Ȃ���̂����炢���̂��v�@�n���N�E�E�B���A���Y�͋��e���ꂽ�l������@���Ȃ₩�Ɏ��Ƃ��Ă���������邭�f�łƂ��č~��Ă������Ƃ��̂��B���܂ł́A�܂��ɌÓT�ł��邱�̋Ȃ́u���Q�v���邱�Ƃ��A�l�Ԃ��̂܂܂��ƃ��b�Z�[�W����B���A�����ă{�u�E�f�B�����̎�����_�i�����ꂽ���Q���r����������
�r�������������������@�E�f�B�E�K�X���[��m���Ă��邾�낤���B�f�B�����́A�����ē��{�ɂ����Ă͉��ѐM�N�̌��`�Ƃ�������ނ́A�P�X�Q�P�N�ɃI�N���z�}�̐Ζ��̒��ɐ��܂�A�I�[�`�[�ƌĂ��I�N���z�}�����̂P�l�Ƃ��ăA�����J�e�n����Q���P�S�Ȃɂ��y�ԍ�i�������������B�E�f�B�́u���Q�v�݂̂Ɏ���̐l��������Ƃ��A���́u�{���̐l���v���܂��Ƃ������B�h���ւ̓��Ƃ��Ắu���Q�v�̑̌��҂ł������B�ނ́A�n���e�B���g�������x�a�ɓ|��̂����Ƃ���߂�܂ł̓I�N���z�}�������I�ɉ̂��A�i���Z���X�E�\���O����ږ��J���҂��͂��߂Ƃ���v���e�X�g�E�\���O�Ɏ���܂ŁA�~��Ă��܂��������Ȗڂł����Ă��̎��R���Łu�{���̐l���v���咣�����B
�@�w���u�E�V�b�N�E�u���[�X�x�ŗL���ȃn���N�͉̂��@�u�ЂƂ̐l���ɏ�������ā@�����������܂�����Ă������Ƃ����ďo���Ȃ��͂Ȃ��̂����A��Ԃ̉����ƌy�����������Ŕ�яo�������Ȃ��Ă��܂��B��яo���Ȃ�������C�������Ă��܂����Ƃ��낤�B���͌N�������Ă��邯��ǁA�Ƃɂ����킩���Ăق�����A���͐��܂�Ȃ���̂����炢���̂��v�@�n���N�E�E�B���A���Y�͋��e���ꂽ�l������@���Ȃ₩�Ɏ��Ƃ��Ă���������邭�f�łƂ��č~��Ă������Ƃ��̂��B���܂ł́A�܂��ɌÓT�ł��邱�̋Ȃ́u���Q�v���邱�Ƃ��A�l�Ԃ��̂܂܂��ƃ��b�Z�[�W����B���A�����ă{�u�E�f�B�����̎�����_�i�����ꂽ���Q���r����������
�r�������������������@�E�f�B�E�K�X���[��m���Ă��邾�낤���B�f�B�����́A�����ē��{�ɂ����Ă͉��ѐM�N�̌��`�Ƃ�������ނ́A�P�X�Q�P�N�ɃI�N���z�}�̐Ζ��̒��ɐ��܂�A�I�[�`�[�ƌĂ��I�N���z�}�����̂P�l�Ƃ��ăA�����J�e�n����Q���P�S�Ȃɂ��y�ԍ�i�������������B�E�f�B�́u���Q�v�݂̂Ɏ���̐l��������Ƃ��A���́u�{���̐l���v���܂��Ƃ������B�h���ւ̓��Ƃ��Ắu���Q�v�̑̌��҂ł������B�ނ́A�n���e�B���g�������x�a�ɓ|��̂����Ƃ���߂�܂ł̓I�N���z�}�������I�ɉ̂��A�i���Z���X�E�\���O����ږ��J���҂��͂��߂Ƃ���v���e�X�g�E�\���O�Ɏ���܂ŁA�~��Ă��܂��������Ȗڂł����Ă��̎��R���Łu�{���̐l���v���咣�����B
����R�A�ނ̋O�Ղ͂U�O�N��̃J�E���^��J���`���[���Ƀf�B�����ȂǂɂƂ��āA�P�̗��O�ł���ے� �ł��蓾���B�j���[���[�N�̃O���j�b�a����B���b�a�ɏo�Ă����f�B�����́A�ނƉ���Ă���B�f�B�����u�������悤�ƂˁA�����������̂Ȃ��ł�����A�E�f�B�ɉ���Ď��͐��U�ōł��ӋC���V�ȋC���ɂȂ�܂����B�v
�ł��蓾���B�j���[���[�N�̃O���j�b�a����B���b�a�ɏo�Ă����f�B�����́A�ނƉ���Ă���B�f�B�����u�������悤�ƂˁA�����������̂Ȃ��ł�����A�E�f�B�ɉ���Ď��͐��U�ōł��ӋC���V�ȋC���ɂȂ�܂����B�v
�@�E�f�B�E�K�X���[���D��ʼn̂����w�z�[�{�[�i���Q�ҁj�̎q��S�x�uGo to sleep you
little hobo/Let the town drift slow by/Can't you hear the steel rail hummin'?
That's hobo's lullaby./Don't think about tomorrow/Let tomorrows come an'
go.Tonight you've got a�@nice warm boxcar./Sate trom all the wind and ��now//Well,I
know the police cause you trouble.They cause trouble everywhere.when you die
and go to heaven.Then you want no policeman there./I know your clothes are town
and ragged. And your hair is turning grey.Lift your hair and smile at
trouble,You'll tind happiness someday.Go to sleep you little hobo.Let the towns
drift slowly by.Don't you feel the steel rails hummin'?That's a hobo's lullaby.�v�@�S�̃��[���̂��Ȃ���q��̂Ƃ�����Q�҂̃��A���Ȑ������̂���B�����̂��Ƃ��S�z�����@�����Ȃ���ɉ߂������Ă䂭���E�E�E�E��������āA�g���u���ɔ��݂����Ă����A�����Ƃ����A���a�ƈ�����������E�E�E�E�v�Ƃ������������ȃI�v�`�j�Y���́A�ڂ���̗�����͂Ă��Ȃ�������B������������������Q�҂̑O�]�́A�Èłł���A���̈Â��͂��̋ȑS�̂��������Ă���B
�@�~��Ă��܂����҂ɂ�鎩�R�A���ꎩ�̂̓����ȉ\���͎��̂悤�ȋǖʂ������Ă���B
�w�����u�����E�{�[�C�x�@�u�E�E�ELate one night in ajungle town.The
weather it was cold and down.He got the chills and he got'em bad They took the
only pal I had He's left me here toramble on Myramblin' pal he's dead and
gone....�v

�@����́A�U�O�N��ɓ��{�ł����тȂ��̂��Ă��Ȃł��邪�A�ꌾ�Ō����Ă��܂��Ȃ�ŖS�̉\���Ƃ������Ƃ��낤�B�ŖS�̉\���ɖڂ����ꂸ�A���邢�́A����������Ȃ��ے肵�@���邢�h���̏����ɂ̂ݎ��_���߂������Ɏ��R�̂���͂����Ȃ��B���ƂƂ��ɂ������Z������ŖS��ė��ւ̉\���̋ǖʁA���ꂪ���̎��R�̂������Ƃ��Ă̎p�Ȃ̂��B����͂���ɐi�B�ŖS�ւ̉\���ƕ\����̂ƂȂ������R�����������u���Q�v���h���ւ̓��ł���������́A���łɌÓT�I�ł����Ȃ��B����ɂ�����w���Q�x�Ƃ́A��蕡�G�ŋ��Ȃ����l���������Ă���B�@�@�@�i���j
�{�u�E�f�B�����w�u�����M���O�E�C�b�g�E�I�[���E�o�b�N�E�z�[���x�i�P�X�U�T�N�j�� ��
��
�w�G�f���̖傩��x
�����̑��z����Ԃɂ�݂ɂ������ށ@�x�b�h�͐�ɂ킽���̂��̂ł͂Ȃ��@�F�B�⑼�̌��m��ʐl�B���@�ނ�̉^�����玫�E���悤�Ƃ���@����͎��ʈȊO��肽�����Ƃ͉��ł��@�ł���悤�Ɂ@�_���Ɋ��S�Ɏ��R�ł��邪�܂܂ɂ����������߂����G�f���̖�̓����ɂ͍ٔ��͂Ȃ��B
�T�l�Ɨ�
�͂����Č��݂̐��̒���M�������l�Ԃ����l����̂��Ƃ��낤�B���\�̐��E�Ƃ�������ς͂P�O�O���ڂ���̋��L���ł���B�����������݂ɂ���A�l�������܍��킹�Đ������邽�߂ɂ͊J������Ƃ����߂Ƃ����K�v�Ȃ悤���B�������A������������������i�D�͂��Ă����Ăڂ����Ώۂɂ��悤�Ǝv���Ă���̂́A�ēc�Ă̏����ɂ���t�����܂̐}���ɕ\�킳���悤�Ȑl�ԂƂ��Ă̐��ʐ����������ł���B�������A�����������قǁA���g�ɂȂ炴������Ȃ����A���ꂪ�K���Ĕ��g���K���������ҁA�܂����ɂ͂Ђ�����Ԃ��Ďg��K�v�Ƃ��邱�Ƃ����X�ł���B
�@��������������ԂɊׂ������A�K���ނ͖���`���\�\�\�����������E��Ԃ̐l�Ԃ������܌��錶���̔@���B����͌���ꂽ�X�y�[�X�Ƃ��Ă̓��퐶������V�����Ė����̍L����ł����Ĉ��ɖ����ĕ`����Ă䂭�B�ڂ��̈ӎ��̒��ɂ����Ăڂ��𗷂ւƂ��肽�Ă錴���͂͏Փ��ł����������m��Ȃ������̖{���I�Ȃ��̂͂ڂ��̑̓��̂��[�݂ɉ������A�����I�ɂ����ς��ĉ��炩�̒�����Ԃ����m��Ȃ����A���̖{���I�Ȃ��̂́A�ڂ��̑̓��̂��[�݂ɉ������A�����I�ɂ����ς������炩�̒��� ��Ԃ�������Ȃ��B�Ȃ�Η����l����ɂ����āA���̐��_�I�������l���邱�Ƃ��Ӗ����邱�Ƃ��낤�B
��Ԃ�������Ȃ��B�Ȃ�Η����l����ɂ����āA���̐��_�I�������l���邱�Ƃ��Ӗ����邱�Ƃ��낤�B
�@���̐��_�I�����������Ԃ��Ă�����ƂɈ������[������B�Љ���̈��ꂫ�́A���R�Ȑl�Ԑ��̓W�J�ł���͂��̐l�Ԑ����������Ƃ������ڂ낰�Ō������̂Ȃ����̂ɂ��Ă䂭�B���[�̓A�C���j�[�ɖ����ď�������̐��E�ւƑz���͂������ēW�J�����B���̏��R�[�X�E�J���`���[���s�������Śk�������̂Ɂu���₶����Ⴈ��̏������ꂽ���́v�Ƃ��������傪����B��邹�Ȃ��}�������\���������[�X�E�J���`���[�̎��_�ł͂��邪�A���̂��炯���o�ɂڂ��͉����l�ԂƂ��đ�Ȃ��̂������Ă��܂����悤�Ȃ����������r�������o����̂��B�ڂ��ɂƂ��Ē�������r�����Ƃ͕\����̂ł���B�т��Ƃ����l�Ԑ��̎��R�ȓW�J����Ȃ��̂̑���Ȃ��ƕs�݊����ꂪ���ꂪ�R�ɂڂ��͖���`���B���Ƃ͏�Ɍ����̎����ɂ����錇�����̏ؖ��ł��莩�Ȃ̓����ɂ��̖����x��������u�����鉽���̂������[�����݂��Ă��邱�Ƃ������Ă����B
�@�����疲�ɂ���Ă��������������Ɍ������A�ڂ��͕����Ă䂭�B�u��������̂ɉ����Č��������Ƃ�߂����߂ɁB���т͒����ɂ����Đ����邽�߂ɗ��ɏo�邱�Ƃ��̂��@�͂����Ĕނ͉���M�����������߂ɋ^��������̂��낤���A�Ƃɂ����P�X�V�O�N�w���R�ւ̒������x�u���̂܂ɂ��������łȂ��悤�ȁ@�͗t�����ɕ����悤�Ɂ@���M�������悤�悤�Ɂ@����������x�A���ɂȂ邽�߂Ɂ@��ĂĂ��ꂽ���E�ɕʂ�������ė����@�M�����������߂ɋ^���Â���B���R�ւ̒���������l�@���R�ւ̒��������������v

�@���Q�Ƃ͖{���I�ɖ����i�p�����ςȂ��o���ςȂ��Ƃ��������̂ł��邪�A�ڂ��͒����ԕ��Q�Ƃ������̂��`�ł��錾�t�������Ă����B���̖��A�悤�₭������ł����̂��A���Q�Ƃ͍~�����ꐶ�U�ɓn�邳���炢�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B���̎O�҂͂ǂꂪ�����Ă����Q�Ƃ������̂𐬂藧�����Ȃ��K�v�����ł���Ǝv���A�܂��~�肽�����炢�ł�������炢�̊��Ԃ����\���ŏo���ςȂ��Ƃ��������Q�Ɨ��Q�Ƃ͕\�ʏ㓯��̂悤�ł���B�������A���̖{���I�ȈႢ�͗��Q�Ƃ͗��l���ˑR�Ƃ��ĎЌ��̂Ƃ̉��炩�̊W��ۂ�����Ԃ������̂ɑ��ĕ��Q�Ƃ͂����ے肵����Ԃł���Ƃ������Ƃ��B�Ō�ɍ~�肽�ꐶ�U�ɂ킽��Ƃ��������t�̑g�ݍ��킹�ł͈Ӗ��͐����Ȃ��B���Ȃ킿�A�����O�̌��t�͂��ꂼ�ꎟ�̂悤�ȈӖ���\�킵�Ă���̂��B�~�肽�Ƃ�drop
out�܂�Љ��o�Ă��܂�����Ԃ�\�킷�Љ�Ƃ͐l�Ԃ̏W���̂ł���A���̐l�ԓ��u�����炩�̊ւ�荇���������Đ�������B����Ȋւ�荇���̒��ōł���b�I�Ȃ̂����Ƃɂ�鋤�ƂƂ��������Ƃ��낤���B�����������ݍ����ɂ���Đl�Ԃ͐H���Ă�����B�܂萶�����邱�Ƃ��Љ��ۏ���Ă���B�Љ��o��Ƃ͂����������W���������邱�Ƃł���B����́A�Љ�ɉ���ӔC�������Ȃ�����Ɂ@���A�Љ�牽�̕ۏ��^�����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��B�ꐶ�U�ɓn��Ƃ͋�̓I�Ȋ��Ԃ�\�킵�Ă���B�����炢�Ƃ͐g�̊�Ƃ���̂Ȃ����ł���B

�@�~�肽��ꐶ�U�ɓn��E�����炢�@���̒��ňꐶ�U�ɓn�邳���炢�Ƃ́i���̂P�j�ŕ��Q�����Ƃ������̂̎��Ԃɂ��čl�����܂ɂӂ�Ă������Ƃł���B�����Ȃ�~�肽�Ƃ͎Љ��o��Ƃ͂���������ΘJ����߂�A�Ƒ�������A��Z����߂�Ƃ��������Ƃ��낤�B�����������������Ď����Ƃ����̂��̂Ƃ̊W��f���点��Ɏ���̂��B�܂��l������̂͌���Ȃ����ւ̏Փ��ł���B���ۂ����܂����قǂɓo�サ���J�E���^�[�E�J���`���[�^���͉��I����S�I�ɂ̓j���[���t�g���q�b�s�[�ɂ��ˏo�I�ɕ\�����ꂽ��A�̓����ł���B����́A�Y�ƌ��Q�⎩�R�j����������炷����I��@�B�I��������l�ԑa�O����b��̑r���������炷�e�N�m�N���[�g�I�S���̎x�z�Ƃ����������ăe�N�m�N���[�g�I�Y�ƎЉ�ɑ���R�c����͂��܂�A�V���ȃ��C�t�X�^�C���̖͍��ɂ܂Ŕ��W���Ă������B�S�ʓI���剻�̎v�z�ł������B���łɏ\�N�߂����j�������̉^���̓W�J�����Ă䂭�ƎO�̒i�K�ɕ�������B�����Z���`���Z�N�u�傢�Ȃ鋑��v�Ƃ���ꂽ�����A���Y�ƎЉ���̓��I���������炯�����������Əd�Ȃ�x�z�I�ȉ��l�ςɑ��鎷�X�ȍU���������I�v���e�X�g�^��������œW�J���ꂽ�B�����郄���O�E���W�J�������|�I�҈Ђ��ӂ�����̂����̎����ł��̃X�^�C���͏]���̌���̌n�ɂ�闝���⋤�������ݗᎦ�I�s�ׁE�ӎ��I�����A���˂Ƃ����Ƃ���B�A���O���������S���̎������B
 �@�����R�~���[�����݂̎����A�����I�E�C���O���u�`����R���J���Ɖ^���̃��H���e�[�W���グ�Ă����ɂ�A�܂��A���ꂪ���܂Ƃ����`�ŏI���������A�V���Ȏ��ɂ����鐶���Ƃ������̂������Ȃ�ɂ����X���ɂ��炾�����o�����l�Ԋv���E�C���O�ɂ���ăR�~���[���^�����W�J����Ă������B�j���[���t�g����_�鐭���ւ̕ϊ��̎��ł���^���͓������̋ǖʂ��}�����B��O���̌��݂̒i�K�ł���B�R�~���[���Ԃ̘A�сA�_���R�~���[���̓s�s�R�~���[���ւ̓]���A��Ď{�݂�ʂ��Ďs���Ƃ̐ϋɓI�ȐڐG�ȂǂƓ���������O���ւ̐Z�����̎������B�@�����@�̐��E�ւ̌X�����܂�B
�@�����R�~���[�����݂̎����A�����I�E�C���O���u�`����R���J���Ɖ^���̃��H���e�[�W���グ�Ă����ɂ�A�܂��A���ꂪ���܂Ƃ����`�ŏI���������A�V���Ȏ��ɂ����鐶���Ƃ������̂������Ȃ�ɂ����X���ɂ��炾�����o�����l�Ԋv���E�C���O�ɂ���ăR�~���[���^�����W�J����Ă������B�j���[���t�g����_�鐭���ւ̕ϊ��̎��ł���^���͓������̋ǖʂ��}�����B��O���̌��݂̒i�K�ł���B�R�~���[���Ԃ̘A�сA�_���R�~���[���̓s�s�R�~���[���ւ̓]���A��Ď{�݂�ʂ��Ďs���Ƃ̐ϋɓI�ȐڐG�ȂǂƓ���������O���ւ̐Z�����̎������B�@�����@�̐��E�ւ̌X�����܂�B
�@���̉^���͌��݁A�����̉₩�ȗl���͎��������̂̊��ɐ�i���́i���ɃA�����J�j�����̓����֊m���������Ƃ�ł����݁A��������^���̂Ƃ��đ������Ă���B���̐V���ȃ��C�t�X�^�C���̊m���ƐV�����R�~���[�����݂ɂ��i��ł���^���̂��������ȑ��݂������Č��݂̎x�z�I�����A�����Ďx�z�I�Љ�\���̑S�ʓI�]���ւ̌����͂Ǝw�E����w�҂�����B
�@�������A���J�E���^�[�J���`���[�ɂ��E�ߑ㉻�̈ӎ�������̂�̌n�����ă��[�����A����ɕ��͂����������͂Ȃ��B�ނ���A�g�����_���ɔނ�̃R�����g�������ɕ��ׂ邱�ƂɂƂǂ߂悤�B�u�ߑ㉻�̑��̓I���ʂ͋A��ׂ��̗��̑r���ł���A��X�̗��z�͌̋��ɋ���悤�ȋ��������̗ǂ����B�ڂ���͖c��A���G����Q�[���V���t�g�i�g�D�j����Q�}�C���V���t�g�i�R�~���[���j��ڎw���B�u���v�ɂ���Ĉ����g�D���Ă�̂́A���Ⴟ�ق���i�A�v�^�C�g�l�X�j���B�����āA�J�����_�[�ɂ���Đl����v����̂͂˂��������̋]�����B�v
�u������v�v��A�v�Z�A�g�D���������i���̑��̃e�N�m���W�[�ɂ��@�B�I�������j�� �͐l�ԂƐ��E�̊W���玩�R����D���|�����B�����́i�����I����ɂ��j�x�z���邩���ɗ������ׂ��ł��葼�҂Ƃ͑��c�������ɏo��ׂ��ł��荇���I�v�l�����t�B�[�����O�ɂ�銴���s�q�����d�v���B�v
�͐l�ԂƐ��E�̊W���玩�R����D���|�����B�����́i�����I����ɂ��j�x�z���邩���ɗ������ׂ��ł��葼�҂Ƃ͑��c�������ɏo��ׂ��ł��荇���I�v�l�����t�B�[�����O�ɂ�銴���s�q�����d�v���B�v
�@���āA���̕ӂɂƂǂ߂�Ƃ��āA�ڂ������̃J�E���^�[�J���`���[�^���ɉ��čł��S���Ђ����͎̂��ӎ��̒��z�⎩�R�Ƃ̍��̂ɂ�鐸�_�ω��Ƃ����|�C���g�ł���B���ӎ��̒��z�⎩�R�Ƃ̍��̂ւ̋�̓I��i�Ƃ͐��I�I���K�j�Y���E���b�N�E�h���b�O�E�������܂ꂽ�����K���≿�l�ς̑��_���E���R���̂��̂ւ̐ڋ߂Ƃ����������Ƃ��������邪�A�������������̂�ʂ��ē��퐶���̒��ʼn�������ꂽ�����I����⎩�ӎ��Ɋ�Â��č�p���Ă���B����܂ł̂��Ⴟ�ق��������_��j�A�l�ԂƂ��Ă̎������Ĕ������悤�Ƃ��������Ƃ��B�����āA�ނ炪���o�������̂Ƃ́A���ӎ��ƍ������Ƃ����C�l�܂�ȋ����̉��ɂ������u���R�I�������̂Ƃ��Ă̂��̂�v�Ƃ����A�₷�炩�Ȏ����Ȃ̂��B
�@�܂��������̐��_�̕ω������Ȃ������ʓI�Ȑ[�܂�𑝂����̐����Ƃ������@�v���Z�X�̃_�C�i�~�X�����J�E���^�[�J���`���[�^���ɑ��Ȃ�Ȃ��B�J�E���^�[�J���`���[�̍s���@���C�t�@�X�^�C���E�咣�i�����Ȃ��̂ɃG�R���W�[�^��������j�́A�S�Ă��̎����F���ł���B
�@����邱�Ƃ�����ɋ��v��������Q�҂̎p�͗���邱�Ƃ������炤���Ƃ��l�Ԃ̎g���ł��邩�̂悤�ɂڂ��ɔ����Ă���B���̗l�ȗ����̂��̂�ړI�Ƃ��錴���͂̐��@���܂��l�����邪�A������v�������Ԃ͎̂��R�̊l����ړI�Ƃ����̋�̓I��i�Ƃ��ė�������Ƃ��������@�ł���B
�@�Љ�ɐ����邱�Ƃ��������E�����Ƃł��肱�̗l�Ȑl�Ԑ��̒����������Ď��R���߂����A���̎�i�Ƃ��ė���I�ԁB���Q�҂͎����������Ƃ��Ď��R�����ߗ��ɏo��B������������ɂ��闷�l�̎p���������ڂ����O�e����X�|�b�g�����ĂĂ���J�E���^�[�J���`���[�ɂ���ĒS�ꂽ���Q�Ƃ������̂��l�����ɉ��ďd�v�Ȍ��ƂȂ��Ă���̂ł���B
�@���������P�̍Ō�ɏ������f�B�����́u�E�E�E�E�E�ނ�̉^�����玫�E���悤�Ƃ���E�E�E�E����͐_���Ɋ��S�Ɏ��R�ł��邪�܂܂ɂ����������߁v�Ƃ��������t�͎Љ�������E�����ɏo�邱�Ƃ���������Ƃ��������R�����߂闷�l�̈ӎ��̏ے��ł���B�ڂ���̓A�����J�̎Ⴋ�Q�l�̐N���u�_���Ȋ��S�Ȃ鎩�R�v�����߂ė��ɏo�������m���Ă���B���̖��́w�C�[�W�[�E���C�_�[�x

1969�N�@���̓j���[�V�l�}�̎���B�J�E���^�[�J���`���[�����W�J���ɑٓ������߂��������B���吧��ɋ߂����̍�i�͐��ނ����n���E�b�h��K�ڂɏ��ƓI�ɂ����Ȑ����������߂�B�v���f���[�X�F�s�[�^�[�E�t�H���_�@�ēF�f�j�X�E�{�b�p�@�t�H���_�͂��̉f��ɂ��Ď��̂悤�ɘb���B�u�C�[�W�[���C�_�[�Ƃ͓암�̌��t�ŏ��w�̕v�̂��Ƃ��B�|�������ł͂Ȃ����̏��ƈꏏ�ɐ������Ă���j�̂��Ƃ������B�y�ɂ���Ă��邩��C�[�W�[���C�_�[���B�A�����J�͂��̃C�[�W�[���C�_�[�ɂȂ��Ă��܂����B���R���p�����ɏo���āA�F���C�[�W�[���C�_�[�ɂȂ����̂��B�����ł������܂����������œ�l�̓��[�^�[�T�C�N���̗��ɏo��B�ێ�I�ȓ암�̓c�ɂ��Ԃ��Ƃ��}���t�@�i���z����l�͈ꌩ���R�������B�������ނ�͑��l�ɏP���A�t�H���_������`���v�e���E�A�����J�̓V���b�g�K���Ō�����T�C�N�����ƂԂ��Ƃщ������B�u���̂��̉f��͎��R�ɂ��Č���Ă���̂ł͂Ȃ��Ď��R�̌��@�ɂ��Č���Ă���̂��B�����������p�Y�����͐������̂ł͂Ȃ��Ԉ���Ă���̂��B�����ŏI�I�ɐ�����������̂́A�����������l�����E�����Ƃ��B���͍Ō�ɂ͎��E���Ă��܂��B�A�����J���s���Ă���̂͂��̎��E���B�t�H���_���������_�Â������A�T�C�N���͒e�ꂽ�悤�Ɏ߂Ɋ����B���傤�ǂ��̎��X�N���[���̃o�b�N�Ƀf�B�����́w�C�b�c�E�I�[���E���C�g�E�}�x�������B�u�E�E�E�E���Ȃ��̐_�o�̒��Ɏ��₪�_���ꂽ�B�������̎���ɂӂ��킵���͂Ȃ��B������Ƃ����ĉ�{�����Ƃ�Y�ꂽ�肵�Ă͂����Ȃ��B���Ȃ��������Ă���̂́A�ނł��ޏ��ł��ނ�ł����邢�͂���ł��Ȃ��E�E�E�E�v
����͍X�ɐi�B�ŖS�ւ̉\���ƕ\����̂ƂȂ������R�������������Q���h���ւ̓��ł���������͂��łɌÓT�I�ł����Ȃ��B�l�炪�^�����Ƃ�m�炸�ɂu�T�C��������Ă�������͋����Ă��܂����B�ڂ���̈ӎ����ق��Ă����ے��Ƃ��Ẵf�B�����≪�т����łɋ����ł����l�̉��y�Ƃł����Ȃ������B�Ȃ�E�f�B�E�K�X���[�̔@���A�₢�Ԃ������f�B�J���ł��邪�R�Ɏ��炪�A�E�g�T�C�_�[�ł������肦�Ȃ������Ƃ����A�E�g�T�C�_�[�̃V���A�X�ȐM�ߐ��͈�̂ǂ��Ɍ�������̂��B
����������ɑ��铚���͎����ɉ��B�_�o�̒��ɓ_���ꂽ����ɑ��鐳���ȉ��ڂ��̓J�E���^�[�J���`���[�̉^���̑��̂̒��Ɍ��o���B�J�E���^�[�J���`���[�̎��Ȕے�̖��A��J���ꂽ�ނ炪�����ĂԂƂ���̎��R�̒n���ɁB
�@���̖{�������R�ɂ���Ƃ������Ƃ����Ƃ���J��Ԃ�����͂Ȃ�������͕K���čD������ȍs����Ԃ������̂ł͂Ȃ��B�G���Q���X�ɂ��Ύ��R�Ƃ͗��j�I�K�R���ɏ]���Ă���p�ł���A�ڂ��̓J�E���^�[�J���`���[�̗��O�̒��ɂ����������R��������B�����ăJ�E���^�[�J���`���[�̒���V�������C�t�X�^�C���ɑ��Ă����Q�Ɠ��l���������������B����ɐ��_�I������Ԃ��l���Ă�������������z�����Ƃ��납�甭�����ڂ���ɂƂ��ė\�z�O�̏�����˂��o���ꂽ�V���ȉ��l�����J�E���^�[�J���`���[�Ƃ������̂͂ڂ��������l����ɂ������ċ������邱�Ƃ͑傫�������B

�@�U�O�N��㔼����V�O�N�㏉���ɂ����đS���E�I�K�͂Ő�i�Y�ƎЉ�Ƀh���}�`�b�N�ɂ̏�ɂ��������̂��B�������E�̎嗬�h���Љ���̃t���X�g���[�V��������̓�����`�I�K���A�܂�u���ɂ̓I���炾���̈ӎu��E�ϗ͂Ȃ����������Ȃ̂��B�v�ƕЕt���@����A�ڂ��͔ނ�̉^����ӎ��ɉ����V��������������B�傫�ȗ��j�I���n���炢���ꂪ���j�I�ɐ�i�I�Ȃ̂��Ƃ������c�_��i�߂�ɂ͗]��ɂ��J�E���^�[�J���`���[�����シ���邩���m��Ȃ��B�������ނ炪�^���̉ߒ��ɉ��ē��B�����u���R�I�������̂Ƃ��Ă̂��̂�v�Ƃ����₷�炩�Ȏ��������菊�Ƃ���������咣�����鎞�A�ڂ��́A�l�ԂƂ��Ă����ł���ׂ��p�Ƃ������̂������Ɋ�����̂��B�����Ŗl�͔ނ�̎咣����ʂ荇���I�v�l�����t�B�[�����O�ł����Č����낤�B�ނ�̎p�Ƃ͗��j�I�K�R�̎��R��������Ȃ��B�����Đ��x��l�ɕ��킳�ꂽ���������ԗ��X�Ȃ��̂��l�Ԃ̌����̗l�ƌ��Ȃ��l�������ߑ㐸�_�̍��{�ɉ�������Ă���l�����Ƃ���Ȃ�ΐl���ނ�̉^���ӎ���E�ߑ�E�������I�Փ��ƌĂڂ��Ƃ�����͖��X�Ɠ`����ꂽ�ߑ㐸�_�̕��y�I�O��ɗ��r������̂ł���A�ǂ��܂ł��ߑ�I�ł���B
�@�ĂсA�R�����g�փJ�E���^�[�J���`���[��S����t���[�N�i���́F���S�Ȃ鎩�R�l�j�����ɂ��Ă��R�����g���u����������������ɑς���̂����낤�B�Q�܂ɗ����蒩�I�ɉ������o����̂ɂȂ낤�B�q�b�`�n�C�N�͈����ǂ���낤�B���x�������Ƃ���Ă�����₩�ɓ����悤�B�ŏ��̗\��v��͔j���邽�߂ɂ���B�v�����āu���͂����������������������ł��B�o����ʂ������܂���v

������ӂŏ�������b�̗�����ӂ�Ԃ��Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B�b�����炪���Ă�₱�����Ȃ��Ă�������B
�@�u����ᔻ�v�Ƃ������ʐ����i���̂����e�[�}�Ƃ͂���͂�ɍ\���͂ɊÂ��_�`�I�Șb����n�܂����w�����_���[�ցx�͐悸�A�ڂ��̂��Ă��闷�A�����Ăڂ��̂�낤�Ƃ��Ă��闷���q�ω����悤�Ƃ��邱�Ƃ���n�܂����B�����Ă��̂��Ƃ͂��̃G�b�Z�C���т����`�[�t�ł�����B
�@�܂��u���̓I�v�Łu�����āv�܂蒷���ԁA�������Łu�M���M���ȁv���Ƃ������Ƃ���A��������E�ɂ܂ł܂�l�Ԃ̈ꐶ�ɖ��Ђ��L�������Q�Ƃ������̂Ɏ��_�����킹�Ă݂��B
�@���ɂڂ������ɂЂ���铮�@�Ƃ������Ƃ��납����ɃJ�E���^�[�J���`���[�ɂ����ĒS��ꂽ���Q�Ƃ����Ƃ���Ɏ��_�����ĂĂ���𐄗��A���@���Ă݂��B�����āA����Ƃ̊֘A����J�E���^�[�J���`���[�̎v�z���A���₻��ȑ�҂�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA���̒��łڂ������ɊS���Ђ��Ƃ�������Ă����B
�@����̓t�H���_���_�����^�╄�ɑ��鐳���ȉƎv��ꂽ�B�i�܂��A�ނ炪����G�R���W�[�^���Ƃ͎����ɉ��Ẵ��C�g���`�[�t�ƂȂ���̂�����B
�@�Ƃ������Ƃł���܂ł̂��炷��������̂͏I���ɂ��Ă����ɂ�����e�[�}�\���Ƃ��Ă̎��R�s�\�ֈڂ��Ă������B
�@�R�s�Ƃ́A�ڂ��ɂ͗��Ǝv����̂��B�o�R�Ƃ����s�ׂ���̉^���̎����̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�������A���㋣�Z�e�j�X�싅�E�E�E�ȂǂƂ͂��������_�̈�ɓo�R�����ꎩ�̂Ől�Ԃ̐����Ƃ������̂��`�����Ă���Ƃ������Ƃ�����B�O�L�̃X�|�[�c�́A����玩�̂Ő����Ƃ������̂��`�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ɑ��A���R�̒��ł̐ςݏd�˂��o�R�Ƃ����s�ׂł���B�����đO�L�̃X�|�[�c�ł͏����������ʏ�]�X�����ɑ��ēo�R�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�l�Ԃ̐����ɗD��̍��Ȃǂ�����킯���Ȃ����炾�B��������悤�Ƃ���l�́A���ȐM�O�̑��҂ɑ��鋭�v�҂ł��邩��ł��邩���͂���ł܂����Љ�ʔO�̐M��҂ł���B�����������Ă͍���͓̂o�R�ɂ����鎖�̂��X�|�[�c�ɂ����镉�ނł���Ƃ������Ƃ�ے肵�悤�Ƃ�����ł͂Ȃ��B����Ƃ���Ƃ͕ʖ�肾�B�܂�A�ڂ������������̂́A�o�R�ɉ��čs���鎩����s���i�炦�����Ȃ���̈ړ��Ƃ����s�ׂ����炩�ɂڂ��ɂƂ��Ă̗��̒�`�̒��ɕ��܂���Ă���Ƃ������ƂȂ̂��B�o�R���X�|�[�c����͂ݏo��Ƃ����̂͒P�ɂ��ꂪ�Ύ��R�̍s�ׂ�����Ƃ��������̂ł͂Ȃ���������Ɗ֘A�����^�œo�R�Ƃ����^�̗����l�Ԃ̉���ɋy�ڂ���Ƃ��������̂ɋN�������ł͂Ȃ����낤���B�Ƃɂ����ڂ��͈ڂ�ς�鎩�R�̒��Ő������邱�Ƃɗ����������Ƃ��Ă̎R���v���̂��B�u�R�s�v�Ƃ������t������B�������A�ڂ��́A���̌��t���������B�ނ���u���R�s�v�ƌĂт����B�R�����{�Ƃ������y�I���������m��Ȃ������Ñ�A�j�~�Y���̎��R�i�ς̒�������ɎR������I�т�����@�@�@���邱�Ƃɑ����̂��Ԃ�����o����B�[�c�v��̕��͂̒��ɍ����Ɋւ���R�����g������B����ɂ��Ɓu�����v�Ƃ�����`�̔����͖����ڍs�ł���Ƃ������L�q����n�܂莟�̂悤�ɏ�����Ă���B�u
 |
|
�W���o���j�E�Z�K���e�B�[�j�iGiovanni Segantini�j |
�����ȑO�̓��{�l�̎��R�ς͐���敗�̗ѐ�̎�Ɏ������ĊJ���ȑ������������`�Ղ͌|�p��i�ɂ������Ȃ��������オ�I����Ď��R�Ȏv�z���g����O�����w�̎��R�`�ʂ�m��̉e���������Ď���ɔ������o���Ă����̂ł��낤�E�E�E�E�v���̌�o�R������ɂȂ�ɂ�č�����������l�������Ȃ�₪�ĎR�ƍ����ƕ��я̂�����l�ɂȂ����B�����Ƃ�������܂ŎG�؈�������Ă��������}���e�B�N�ȕ��i�Ƃ��Ė𗧂��_�k���n�̕��������̍r���n���q��Ƃ����V�������t�ŌĂ�A�����̎R�X���Z�K���e�B�[�j�̊G�̗l�ɒ��߂���l�ɂȂ��āA���͂⍂���ꡂ͓o�R�̑傫�ȕ�����߂Ă��܂����B�E�E�E�E�v���������p������w�L�����̂��o�b�N�p�b�L���O�̎v�z�ł���B�����ł͎R�s���͓o�R�͑Ύ��R�̃A�E�g�h�A���C�t�̈�Ƃ��ĂƂ炦����B������u���{�l�̐S�̒�ɂ͂����R���������v�Ƃ������m�F���������ɂƂ肩�킵�ď�����Ă������ނ́w���{�S���R�x�ɑ��Ă������ʂ�������Ȃ����̂�������B�Ⴆ�A���̒��ɂ�����m�������̗��P�x�Ɋւ��Ă��ނ������o�������̎����ނ�����͂������瓌�ɃI�`�J�b�p�P�`�����x�ւƑ����Ő��ɓ_�݂�����ׂȎ��R�ɒ��ڂ���ނ��S���R���咣����Ȃ�ڂ��͕S���R����咣���悤�B���������p������[�c�v��̂��Ƃ������Ă�ł͂Ȃ��B�ڂ���̓��ɂ��ݍ���ł���R�x��_��̎��R�Ό��Ƃ������p���ɉ��Ă̓q���E�E�H�[�N�E�r��̂����炢�E�g���b�L���O�Ƃ��������z�͏o�Ă��Ȃ��B

�@�ڂ��̓A�W�A�̒�����q�}�����݂̂�I�яo������ɂ̂ݎ���������q�}�����̕�Ȃ邷����ł��肻�����X�Ƃ��ĕ�ݍ��ރA�W�A�嗤�Ɏ������邾�낤�B�Q���[�g�����炸�̐l�Ԃ̖ڂ���͎R�͋���ł���S�Ă��w���������ڕW���肤��B���������x�Q�����[�g���̏��͎R�͂������Ȏ��R�̂Ђ��ɂ����Ȃ��B�R�s�Ɍ����邱�Ƃ̂Ȃ����R�s�Ǝ��R�I�R�X���|���^�j�Y�����B�R�Ƃ͎��R�̈�`�Ԃɂ����Ȃ��B
�@�����Ăڂ��̗��ɉ��Ă�����R�s���܂߂Ă̎��R�s�͌��݂��̎嗬���߂Ă���l���B����́A�ڂ��̗��ɑ���w�W�̓��u���̓I�v�u�M���M���ȁv�Ƃ������������Ă����B